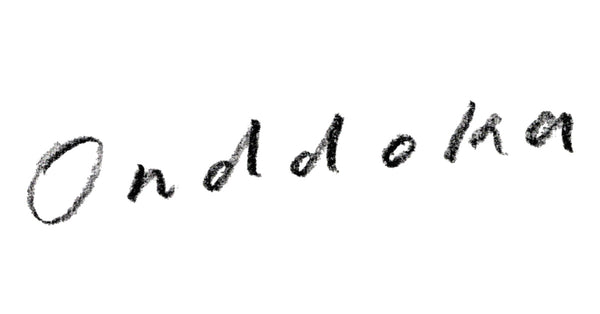고양이의 여름 버티를 방지하기 위해 | 편안하게 보내는 팁과 궁리

공유
고양이의 여름 버티란?
드디어 여름 프로덕션입니다. 올해도 무더위가 계속 될 것 같네요. 사람의 생명과 관련된 이 위험한 더위는 고양이의 건강을 해칠 수 있습니다. 실내를 지키고 있어도 여름 버티를 일으킬 수 있다는 것을 알고 계십니까?
여름 버티는 아프지 않습니다. 여름의 더위로 자율 신경이 흐트러져, 식욕 부진이나 신체가 나른하다고 하는 컨디션 불량이 되는 것을 「여름 버티」라고 부르고 있습니다. 급격하게 컨디션을 무너뜨리는 열사병과는 달리, 며칠에서 몇 주에 걸쳐 만성적으로 일어나는 것이 특징입니다.
 여름 버티의 원인은?
여름 버티의 원인은?
사람과 마찬가지로 급격한 실온 상승이나 다습이 여름 버티의 원인이 됩니다. 고양이는 육구와 코의 일부에만 땀샘이 있기 때문에 사람처럼 땀을 흘리고 기화열에 의해 체온을 낮추기가 어렵다고 합니다. 게다가, 일본의 여름은 다습하고, 공기 중에 수분이 많이 포함되어 있기 때문에, 약간의 땀이라도 충분히 증발할 수 없습니다. 그 결과, 신체에 열이 가득, 여름 버티를 일으킵니다.
또한 더위뿐만 아니라 냉방의 너무 효과도 컨디션을 무너뜨릴 수 있습니다. 에어컨의 냉기는 아래에 쌓이기 때문에 바닥에서 차가운 고양이에 냉기가 맞아 버리기 때문입니다.
 여름 버티를 일으키기 쉬운 고양이종
여름 버티를 일으키기 쉬운 고양이종
모든 고양이가 여름 버티를 일으킬 가능성은 있지만, 그 중에서도 피모가 길고 열이 담기 쉬운 긴 모종 , 짧은 모종에서도 피모가 2층 구조로 되어 있는 더블 코트 , 골격상 호흡이 어려운 코가 부서지는 단두종은 여름 버티를 일으키기 쉽다고 합니다. 그 밖에도, 신체가 아직 완성되지 않은 새끼 고양이 , 신체 기능이 저하되고 있는 시니어 고양이 , 병으로 면역력이 떨어지고 있는 고양이 , 뚱뚱한 기미의 고양이도 체온 조정이 어렵고, 컨디션을 무너뜨리기 쉽습니다. 이 아이들은 열사병에 걸리기 쉽기 때문에주의하십시오.
여름 버티의 증상과 열사병의 차이
여름 버티에는 특징적인 증상이 있습니다. 고양이는 본능적으로 컨디션이 나쁜 것을 숨기는 습성이 있기 때문에, 애 고양이의 무언의 사인을 놓치지 않는 것이 중요합니다. 또, 비슷한 것 같고 다른 열사병과의 차이도 해설하네요.
【여름 버티의 증상】
여름 버티를 일으키면 다음과 같은 증상이 나타납니다.
 식욕이 떨어진다
식욕이 떨어진다
더위 때문에 위장의 작용이 약하고 식욕이 떨어질 수 있습니다. 평상시는 잘 먹는 아이가 밥을 남기거나, 전혀 먹지 않게 되면 요주의입니다.
몹시
식욕이 떨어지면서 체력도 떨어지고, 날씬하게 해 움직임이 둔해집니다.
정리하지 마라.
그루밍은 신체를 청결하게 유지하는 것 외에도 타액으로 머리카락을 적시고 기화열로 체온을 낮추는 역할도 있다고 한다. 여름 버티에서 신체에 열이 가득 차면 타액이 나오기 어려워, 정리할 수 없기 때문에, 체온을 낮출 수 없게 됩니다. 머리카락이 없어질 수도 있습니다.
마시는 물의 양과 소변의 양이 감소
소변의 양이 줄어들면 탈수 증상을 일으킬 수 있습니다. 이 상태가 오래 지속되면 신장과 비뇨기 계통의 질병에 걸릴 위험이 높아집니다.
설사나 구토를 하고 있다
더위로 소화기계에 부담이 가기 때문에 일어나는 증상입니다. 여러 번 지속되면 탈수 증상이나 다른 질병에 걸릴 수 있습니다.
【열사병의 증상】
하아하아와 고통스럽게 호흡을 하고, 충혈을 하고 있다고 하는 증상이 있는 경우는, 열사병까지 진행하고 있을 가능성이 있습니다. 게다가, 거품이나 누구를 입에서 내고 있으면 위험한 상태입니다. 눈치챘을 때에는 증상이 진행되고 있었다…
여름 버티의 예방책
고양이는 스스로 환경을 바꿀 수 없습니다. 여름 버티를 일으키기 어려운 방의 상태를 만들 수 있는 것은 주인 뿐입니다. 다양한 대책을 하고 사랑 고양이를 지켜 줍니다.
 【실온과 습도의 관리】
【실온과 습도의 관리】
첫째, 에어컨과 제습기 등을 사용하여 고양이에게 최적의 실내 온도와 습도를 유지하는 것입니다. 일본의 여름 평균 습도는 50~60%로 알려져 있으며, 최고로 75%가 될 수도 있습니다. 고양이를 위해서는 일반적으로 습도는 50% 전후가 권장되고, 연중 권장 실온은 20~23℃ 전후 입니다. 여름은 좀 더 높아도 괜찮습니다만, 공조 관리는 확실히 실시해 주세요.
냉방을 걸 때는 바람의 방향을 조정하거나 서큘레이터로 공기를 순환시키는 등 고양이에 냉기가 직접 닿지 않도록하는 것도 중요합니다.
【수분을 보급시킨다】
수장을 곳곳에 늘리거나 자동 급수기를 이용하여 수분을 섭취하도록 합시다. 흐르는 물에 관심을 보이는 아이도 있다고합니다. 다만, 신체에 좋을 것 같다고 해서, 마그네슘의 함유량이 높은 해양 심층수나 해외에서 판매되고 있는 특수한 경수는 주지 말아 주세요. 마그네슘으로 인한 스트루바이트 요석증이 될 위험이 있습니다. 또한, 거주 지역에 따라 차이가 있지만, 경도가 높은 수돗물도 결석이 될 수 있으므로주의가 필요합니다. 또한 수분 함량이 많은 액상 간식이나 습식 후드를 주는 것도 수분 보급에 도움이 됩니다.
 물을 너무 많이 마시지 않으면 용기가 마음에 들지 않을 수 있습니다. 다양한 용기를 사용하여 원하는 용기를 찾으십시오.
물을 너무 많이 마시지 않으면 용기가 마음에 들지 않을 수 있습니다. 다양한 용기를 사용하여 원하는 용기를 찾으십시오.
【브러싱이나 서머컷을 한다】
칫솔질하면 고양이의 몸에 쌓인 열을 조금이라도 밖으로 낼 수 있습니다. 머리와 머리 사이에 공기가 들어가서 체감 온도가 떨어지기 때문입니다. 특히, 열이 가득 차기 쉬운 장모종의 아이는, 브러싱과 함께 서머컷을 하는 것도 하나의 방법입니다. 다만, 서머컷은 피부가 햇빛에 노출되기 쉬워지므로, 외출시에는 옷을 입을 수 있는 등 자외선 대책을 유의해 주세요.
 또한, 색소가 얇고 피부염을 일으키기 쉬운 흰 고양이 등의 경우는, 집안에 있어도, 창에 UV 컷 필름을 붙이거나 차광 커튼을 사용하거나 하는 궁리가 필요하게 됩니다.
또한, 색소가 얇고 피부염을 일으키기 쉬운 흰 고양이 등의 경우는, 집안에 있어도, 창에 UV 컷 필름을 붙이거나 차광 커튼을 사용하거나 하는 궁리가 필요하게 됩니다.
【냉감 상품을 준다】
고양이가 뜨거울 때 차가운 물체를 몸에 닿게 하여 열을 놓치게 됩니다. 항상 자고있는 침대에 냉감이있는 담요와 제습 상품을 플러스하는 것이 좋습니다. 더울 때 빨리 잠자리에 갈 수 있도록 문을 비워 두십시오.
여름 버티를 다루는 방법
만전의 예방책을 강구해도, 평소와 다르다는 행동을 볼 수 있으면, 빨리 병원을 진찰합시다. 탈수 증상이 있는 경우는 점적을, 설사나 구토의 증상이 있는 경우는, 약의 처방이나 요법식 등을 제공해 줄 수 있습니다.
관련 기사: Column 「습도에 약한 고양이를 위한 쾌적한 공간 만들기」
 Onddoka 상품
Onddoka 상품
일년 내내 사용할 수 있는 천연 소재의 침대, 제습할 수 있는 매트나 베개의 준비도 있습니다. 올 여름은 시원한 블랭킷도 라인업에 합류했습니다.
또, 통상의 목걸이에 가세해, 새롭게 시원감의 목걸이도 만들었습니다. 사랑 고양이가 편안한 여름을 보낼 수 있도록 꼭 도움을주십시오.