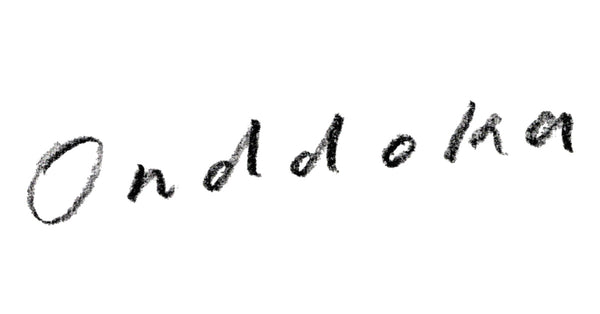湿度に弱い猫のための快適な空間づくり

Share

梅雨の多湿は大敵
湿度が一気に上がる梅雨。ジメジメとした日が続くと体調を崩しがちになりますよね。実は猫も、人間と同じようにこの季節には敏感です。皮膚がベタついて機嫌が悪くなったり、寝つきにくくなったり。さらに、食欲不振になることもあります。その結果、体力が落ち、さまざまなトラブルに見舞われることも。今回は、猫がなぜ湿度に弱いかという理由から、かかりやすい病気や湿度対策までを解説します。

猫が湿度に弱い理由
猫の先祖のリビアヤマネコは砂漠地帯で暮らしていたため、乾燥した暑さには強い傾向があります。でも、日本のような高温多湿の気候は苦手。肉球にしか汗腺がなく熱を逃しにくいうえ、湿度が上がると空気中の水分量が増えて、汗が蒸発しにくくなるからです。また、グルーミング時の唾液の水分が、湿度で蒸発しにくくなるのも理由の一つ。猫は、唾液が蒸発する時の気化熱で体温を下げているのです。

最適な室温と湿度は?
では、どれくらいの室温と湿度が良いのでしょうか。環境省がまとめた「動物取扱業における 犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」※1によると、一般的には室温は20~23℃前後、湿度は50%前後が推奨されています。ただし、湿度に弱い子の場合は、より涼しくする必要があるとのこと。その他、猫種や習性、個体ごとの身体の特徴や健康状態によっても、最適な室温や湿度は変わりますので、愛猫にとってのベストを見つけてくださいね。
ちなみに、冬は湿度が下がるから安心と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、反対に乾燥が問題になります。湿度が20%を下回ると、静電気が起こりやすくなり、ブラッシングの際痛みを伴うことも。また、十分に水分摂取ができていないと泌尿器系の病気を発症することがあります。猫は暖かい場所で動かなくなり、水がある場所へ移動しなくなるので、気をつけてあげましょう。
多湿がもたらす健康被害
次に、梅雨から夏にかけて発症しやすい主な病気を説明します。

1.熱中症
身体の中の熱がこもり、体温が上昇することで起こるというメカニズムは、人間と同じ。口を開けてハアハア息をするようになったら要注意です。特に、長毛種や仔猫、シニア猫、太り気味の猫、骨格上呼吸がしづらい鼻がつぶれている短頭種は、かかりやすいといいます。
2.ノミやダニが原因の病気
気温が13℃になるとノミが、20℃でダニが活発になり、湿度が上がればより繁殖するので、いつも以上に配慮が必要です。たとえば、以下のようなものがあります。
・ノミアレルギー性皮膚炎
首から背中、おしりにかけて、赤い発疹が出て、強いかゆみを伴います。かきむしってしまい、脱毛や出血が見られる場合も。
・疥癬、耳疥癬(耳ダニ)
強いかゆみで、激しく頭を振ることがあります。黒っぽい耳あかが出るのも特徴のひとつ。
3.真菌が原因の病気
真菌はいわゆるカビで、梅雨は増殖の季節です。酵母菌、糸状菌、担糸菌に分類され、人の食べ物に効果的に使われる無害なものもありますが、有害なものもあるのです。
・皮膚糸状菌症
糸状菌が原因で、顔、耳、手足で脱毛し、皮膚がかさかさしたりブツブツができたりして、強いかゆみを伴うこともあり。
・マラセチア性皮膚炎やマラセチア性外耳炎
酵母菌が異常に繁殖して発生する病気です。皮膚や耳が赤くなりかゆくなります。
その他に、毛が蒸れることで急性湿性皮膚炎(ホットスポット)を発症したり、アトピー性皮膚炎が悪化したりすることもあります。かゆがっている子の姿を目にするのは、本当につらいものですよね。
適切な室内環境を保つために
でも、飼い主さんのちょっとしたがんばりで、愛猫を大敵から守ることができるんです。ベストな室温と湿度を保つために、ぜひ以下のことをやってみてください。

・こまめに換気をする
こもった湿気を室外に逃がすため、窓やドアを2カ所以上開け、風の通り道を作ります。
・寝床を涼しい場所に移動させる
風通しがいい所、日が当たらない所を選んで寝床を置きましょう。その際のポイントは、エアコンの風が直に当たらない場所にすること。身体が冷えすぎても体調を崩してしまいます。
・エアコンや除湿機を使う
エアコンの除湿機能や室温設定を使えば確実です。あるいは、除湿機や室内に洗濯物を干す時に使う置き型の衣類乾燥除湿機も湿度の設定ができます。短時間で洗濯物が乾き、除湿もしてくれて一石二鳥。
・除湿剤を置く
設置タイプや吊り下げタイプなど、いろいろな形状があります。寝床の場所に応じて使い分けてくださいね。
さらに、吸湿・放湿効果の高い素材のマットや枕を寝床に置いてあげれば、最適な環境を整えることができますよ。
愛猫の「無言のサイン」に気をつけよう
たとえば、突然寝る場所を変えたら?もしかしたら、湿気で寝床の居心地が悪くなっているのかも。長雨の時に、念入りにグルーミングを始めたら?体温調整ができていない可能性があります。特に長毛種は皮膚が蒸れて湿疹を起こしやすく、舐めハゲが出来てしまうこともあるのだとか。猫は言葉が話せないので、不快だったり具合が悪かったりしても伝えられません。「あれ?変だな」と思ったら、すぐに対応してあげましょう。

Onddokaの除湿マットと枕
Onddokaでは、木綿の約7倍、シリカゲルの2倍の吸湿能力があるわた状の繊維を使用したベルオアシス®︎素材のマットや枕、保温保冷効果があるムートン枕のご用意がございます。外布は天然素材なので夏でもサラッとした気持ちいい肌ざわり。消臭性にも優れています。ベッドとセットのデザインもあるので、ご覧になってみてください。

※1<参考>動物取扱業における 犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0305a/full.pdf