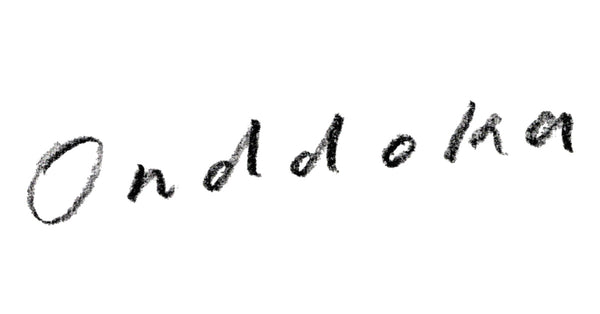Onddokaのネームチャーム
もしもに備えて首輪と一緒に
猫はとてもデリケートな動物です。災害が起こると、ものが落ちてきたり壊れたりする音に驚いて、家の外に飛び出すことがあります。数日後に、自分で戻ってくることもありますが、そのままどこかに行ってしまい、見つからないこともあるのだそう。
「うちは日頃から戸締りをしているから、大丈夫」と思っている飼い主さんはいませんか?日頃からどんなに備えをしていても、有事の際には予期せぬことが起こるものです。
猫が逃げてしまう原因は、窓や戸を開け放していたからだけではないのだとか。能登半島地震では、激しい横揺れで玄関の戸が徐々に開き、逃走してしまった事例があったそうです。また、飼い主さんが外出中に被災して家が倒壊すれば、外に出るしかなくなります。飼い主さんと家にいて同行避難できたとしても、避難所に受け入れてもらえないかもしれません。幸運なことに受け入れてもらえたとしても、環境になじめずにどこかに隠れてしまうことも考えられます。いろいろなケースで、行方不明になる可能性があるのです。

もし、保健所などに保護されたとしても、首輪がなく連絡先もわからないと、野良猫と間違われることがあります。ホームページで猫の収容を知らせる公示期限はわずか数日。飼い主さんが見つからず、別の人の手に渡ることが少なくないといいます。病気やケガで治る見込みがないと、苦しみから解放してあげるという観点で殺処分になってしまうことも。
東日本大震災で保護された動物のうち、迷子札をつけた犬は100%飼い主さんのもとに戻っています。狂犬病予防法により義務付けられた、鑑札と狂犬病予防注射済票の装着によっても、連絡先が判明しているようです。残念ながら、迷子札をつけた猫はいませんでした。※

Onddokaのネームチャーム
猫にとって首輪はストレスになる存在です。存在感のある迷子札をつけると、もっと嫌がるかもしれません。
Onddokaでは、猫の負担になりにくい小さくて軽量なネームチャーム(迷子札)のオーダー会を、毎月1日から3日に開催しています。

1.「ONddoka order Name Charm(首輪用)」の特徴
猫の身体に合わせた小さくて軽い真鍮製のプレートに、お名前と電話番号を刻印させて頂きます。刻印加工は、脱走した時に汚れても文字が不鮮明にならないメリットがあります。

2.選べる装着方法
「Order Name Charm(首輪用)」は、フックか丸カンのいずれかで首輪に装着が可能です。お手持ちの首輪や用途に合わせてお選びください。
・フックタイプ
着脱が簡単なので、有事の際には手早く装着することが出来ます。また、首輪をつけ替える機会が多い場合や、長毛種でチャームが隠れる心配のある場合におすすめの仕様です。
・丸カンタイプ
全体の長さが短い為揺れが少なく、猫のストレスになりにくい仕様です。装着にはラジオペンチなどの道具が必要となりますが、首輪に慣れていない猫には特におすすめです。
3.装着方法と首輪の組み合わせ
以下は、首輪の種類に合わせた、おすすめの組み合わせです。
・猫にやさしいコットン首輪/リボン・・・両タイプ装着可能、チャームが正面に向くのは丸カンタイプ
・猫にやさしいコットン首輪/リボンなし・・・両タイプ装着可能、チャームが正面に向くのは丸カンタイプ
・猫にやさしいコットン首輪/フリル・・・フックタイプのみ装着可能
・猫にやさしいコットン首輪/チョーカー・・・両タイプ装着可能
・猫にやさしいコットン首輪/スタイカラー・・・フックタイプのみ装着可能
※「フレンチノット刺繍のフリル首輪」以外のすべての首輪につけられます。

*真鍮素材の安全性と取り扱いについて
重金属と違い、真鍮には身体に悪影響を及ぼす金属毒性がないので、猫が舐めても安心です。また、表面に緑青というサビが生じることがありますが、大量に摂取しなければ無害です。
鍮は時間が経つと、黒みがかった渋い色合いに変化します。独特の味わいとしてお楽しみ頂ければと思います。気になる方は、金属磨きを使えば、輝きが戻ります。
<参考>
環境省「東日本大震災におけるペットの被災概況 」https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508c/01.pdf
能登半島地震で家から飛び出した猫の事例
https://sippo.asahi.com/article/15109294
真鍮の金属毒性について 株式会社新進
https://sus-shinshin.co.jp/column/about-the-nature-of-brass/
緑青の毒性について 銅の安全性
https://www.jcda.or.jp/learning/safety/index.html
殺処分について
環境省、東京都動物愛護保護センター、大阪府動物愛護管理センターに電話取材