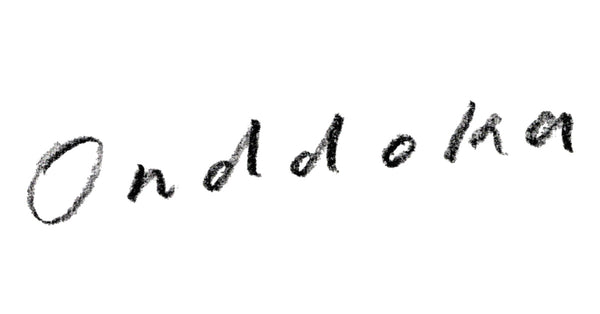ニュース
- 2026.1.6 合同展「MAITE -マイテ-」開催のお知らせ
- 2025.12.31 冬季休業のお知らせ
- 2025.12.27 Name charm(迷子札)オーダー会のご案内(1月)
It's new!
-
猫にやさしいコットン首輪/リボン【Liberty/Clementine】
通常価格 ¥2,420 JPY通常価格単価 / あたり -
猫にやさしいコットン首輪/リボンなし【Liberty/Clementine】
通常価格 ¥2,200 JPY通常価格単価 / あたり -
猫にやさしいコットン首輪/フリル【Liberty/Clementine】
通常価格 ¥2,860 JPY通常価格単価 / あたり -
猫にやさしいコットン首輪/リボン【ドットミニヨン/シックラベンダー】
通常価格 ¥2,310 JPY通常価格単価 / あたり -
猫にやさしいコットン首輪/リボンなし【ドットミニヨン/シックラベンダー】
通常価格 ¥2,090 JPY通常価格単価 / あたり -
猫にやさしいコットン首輪/フリル【ドットミニヨン/シックラベンダー】
通常価格 ¥2,200 JPY通常価格単価 / あたり
季節のおすすめ
-
猫のためのスプリングラムスキンラグ【ブラウン】
通常価格 ¥16,500 JPY通常価格単価 / あたり -
猫のための小さなムートンまくら【ブラウン/Stripe】
通常価格 ¥4,620 JPY通常価格単価 / あたり -
猫のためのスプリングラムスキンラグ【オフホワイト】
通常価格 ¥16,500 JPY通常価格単価 / あたり -
猫のための小さなムートンまくら【ホワイト/Liberty】
通常価格 ¥4,620 JPY通常価格単価 / あたり -
Wool Cat Blanket (ウールキャットブランケット)【Melange Greige】
通常価格 ¥6,600 JPY通常価格単価 / あたり -
Wool Cat Blanket (ウールキャットブランケット)【Brick Orange】
通常価格 ¥6,600 JPY通常価格単価 / あたり -
Wool Cat Blanket (ウールキャットブランケット)【Melange Light Gray】
通常価格 ¥6,600 JPY通常価格単価 / あたり -
Wool Cat Blanket (ウールキャットブランケット)【Melange Gray】
通常価格 ¥6,600 JPY通常価格単価 / あたり
コラム
すべてを表示する-
COLUMN

防災の日に考える、猫と一緒に避難するための備えとは?
目次を表示する 防災の日の意義とは? 9月1日は「防災の日」です。1959年の9月26日に起こった「伊勢湾台風」で戦後最大の被害を被ったことがきっかけとなり、災害に対する意識を高めるため、翌年の6月に創設されました。関東大震災が発生したのが1923年9月1日だったこと、台風が上陸しやすい「農家の厄日」が、立春から数えて二百十日の9月1日前後であることから、この日が選ばれたそうです。また、防災の日を含む一週間は防災週間と定められています。企業や学校で防災訓練を行ったことがある人もいるかもしれませんね。 今回は、年に1度のこの時期に、猫のための防災について考えてみたいと思います。猫も大切な家族です。人と同じように災害に対する備えが必要です。 災害で行方不明になる猫たち 2011年3月に起こった東日本大震災では、たくさんの猫が驚いて家から飛び出し、行方不明になりました。津波の警報が出て避難の準備をする時間がなく、被災地に取り残された猫も数多くいたそうです。 日本は自然災害が多く、この後にも2016年4月に熊本地震、2024年1月には能登半島地震など大きな地震が頻繁に起こっています。災害が起こるたびに、同じような被害に遭う猫たちがいるのが現状です。 運良く保護され、保健所や動物愛護センターに収容されたとしても、身元を確認するものがなく、家に帰れない猫も少なくありません。 家の中の防災と避難先の確認 そのような災害はいつどこで起こるかわからないもの。身近で起こることを想定して、日頃から備えをしておくと安心です。 まずは、家の中の防災について見直してみましょう。地震が起こっても、被害が最小限で済むよう、家具には転倒防止器具をつけるなどして、普段から住まいの耐震化を進めておきたいものです。そのうえで、猫の寝床は、落下物の危険がない安全な場所に置いてください。また、小さな地震があった時、愛猫が逃げ込んでいる特定の場所があれば、そこに危険が及ばないよう、周囲を整えておきます。在宅避難となった場合でも、耐震対策を行なっておけば、いざという時心強いはずです。 次に、自宅から近い避難所の場所と避難経路、避難所のルールを確認します。東日本大震災を契機として、飼い主さんと一緒に避難する同行避難が推奨されるようになりましたが、お住まいの行政のホームページなどで調べておくと確実です。同行避難は、基本的に猫をケージやキャリーバッグに入れることが条件で、人とは違うスペースでの管理になります。ペット用品は飼い主さんが準備しなければなりません。 避難所で過ごすための最低限の備え では、災害時に避難所に行くことになったら、どんなものを持っていけばいいのでしょうか?避難所では人命が優先され、ペット用品は届かないか、届いたとしても遅くなることが多いといいます。約1週間は届かないと想定して、必需品はできるだけ多めに用意してください。以下に、避難の際にぜひ持参してほしいものをご紹介します。 1.フード できれば3日分以上を、療法食なら7日分以上が必要です。ウエットフードは、ゴミが少ないレトルトパウチを。非常用のフードは定期的に賞味期限をチェックしておいてください。最近は、普段のフードを使いながら備蓄するローリングストックという方法も注目されています。 2.水 猫の結石の原因にもなるので、硬水のミネラルウォーターでなく、軟水が欠かせません。最低5日〜1週間程度の量が要ります。 3.容器 できればフード用と水用の2つを用意してください。軽量で割れない素材のものがいいですね。 4.キャリーケース 避難先でストレスなく過ごせるように、猫の数だけ揃えたいものです。 5.ポータブルトイレと猫砂&処理用スコップ 猫砂にそれまで使っていたものを少し入れると、自分の排泄物のにおいがするので、新しいトイレでもスムーズに用を足してくれます。 6.首輪と迷子札 いつも身につけている場合は不要ですが、予備があると安心です。 7.薬と健康手帳 持病がある場合は、病院で多めに処方してもらい、薬も常備しておきます。健康な子でも、ワクチン接種歴や体質、持病などをわかるようにして健康手帳にまとめておくと万全です。 ※その他、ケージ、タオル、毛布、ペットシーツ、ビニール袋、リード付きのハーネスなどもあれば便利です。また、脱走した時のために、特徴がよくわかる愛猫の写真を用意することをおすすめします。 災害が起こった時にすぐに持ち出せるよう、これらはバッグなどにひとまとめにしておくと、落ち着いて行動できます。...
防災の日に考える、猫と一緒に避難するための備えとは?
目次を表示する 防災の日の意義とは? 9月1日は「防災の日」です。1959年の9月26日に起こった「伊勢湾台風」で戦後最大の被害を被ったことがきっかけとなり、災害に対する意識を高めるため、翌年の6月に創設されました。関東大震災が発生したのが1923年9月1日だったこと、台風が上陸しやすい「農家の厄日」が、立春から数えて二百十日の9月1日前後であることから、この日が選ばれたそうです。また、防災の日を含む一週間は防災週間と定められています。企業や学校で防災訓練を行ったことがある人もいるかもしれませんね。 今回は、年に1度のこの時期に、猫のための防災について考えてみたいと思います。猫も大切な家族です。人と同じように災害に対する備えが必要です。 災害で行方不明になる猫たち 2011年3月に起こった東日本大震災では、たくさんの猫が驚いて家から飛び出し、行方不明になりました。津波の警報が出て避難の準備をする時間がなく、被災地に取り残された猫も数多くいたそうです。 日本は自然災害が多く、この後にも2016年4月に熊本地震、2024年1月には能登半島地震など大きな地震が頻繁に起こっています。災害が起こるたびに、同じような被害に遭う猫たちがいるのが現状です。 運良く保護され、保健所や動物愛護センターに収容されたとしても、身元を確認するものがなく、家に帰れない猫も少なくありません。 家の中の防災と避難先の確認 そのような災害はいつどこで起こるかわからないもの。身近で起こることを想定して、日頃から備えをしておくと安心です。 まずは、家の中の防災について見直してみましょう。地震が起こっても、被害が最小限で済むよう、家具には転倒防止器具をつけるなどして、普段から住まいの耐震化を進めておきたいものです。そのうえで、猫の寝床は、落下物の危険がない安全な場所に置いてください。また、小さな地震があった時、愛猫が逃げ込んでいる特定の場所があれば、そこに危険が及ばないよう、周囲を整えておきます。在宅避難となった場合でも、耐震対策を行なっておけば、いざという時心強いはずです。 次に、自宅から近い避難所の場所と避難経路、避難所のルールを確認します。東日本大震災を契機として、飼い主さんと一緒に避難する同行避難が推奨されるようになりましたが、お住まいの行政のホームページなどで調べておくと確実です。同行避難は、基本的に猫をケージやキャリーバッグに入れることが条件で、人とは違うスペースでの管理になります。ペット用品は飼い主さんが準備しなければなりません。 避難所で過ごすための最低限の備え では、災害時に避難所に行くことになったら、どんなものを持っていけばいいのでしょうか?避難所では人命が優先され、ペット用品は届かないか、届いたとしても遅くなることが多いといいます。約1週間は届かないと想定して、必需品はできるだけ多めに用意してください。以下に、避難の際にぜひ持参してほしいものをご紹介します。 1.フード できれば3日分以上を、療法食なら7日分以上が必要です。ウエットフードは、ゴミが少ないレトルトパウチを。非常用のフードは定期的に賞味期限をチェックしておいてください。最近は、普段のフードを使いながら備蓄するローリングストックという方法も注目されています。 2.水 猫の結石の原因にもなるので、硬水のミネラルウォーターでなく、軟水が欠かせません。最低5日〜1週間程度の量が要ります。 3.容器 できればフード用と水用の2つを用意してください。軽量で割れない素材のものがいいですね。 4.キャリーケース 避難先でストレスなく過ごせるように、猫の数だけ揃えたいものです。 5.ポータブルトイレと猫砂&処理用スコップ 猫砂にそれまで使っていたものを少し入れると、自分の排泄物のにおいがするので、新しいトイレでもスムーズに用を足してくれます。 6.首輪と迷子札 いつも身につけている場合は不要ですが、予備があると安心です。 7.薬と健康手帳 持病がある場合は、病院で多めに処方してもらい、薬も常備しておきます。健康な子でも、ワクチン接種歴や体質、持病などをわかるようにして健康手帳にまとめておくと万全です。 ※その他、ケージ、タオル、毛布、ペットシーツ、ビニール袋、リード付きのハーネスなどもあれば便利です。また、脱走した時のために、特徴がよくわかる愛猫の写真を用意することをおすすめします。 災害が起こった時にすぐに持ち出せるよう、これらはバッグなどにひとまとめにしておくと、落ち着いて行動できます。...
-
COLUMN

猫の夏バテを防ぐために|快適に過ごすヒントと工夫
目次を表示する 猫の夏バテとは? いよいよ夏本番です。今年も猛暑日が続きそうですね。人の命に関わるほどのこの危険な暑さは、猫の健康も損なうことがあります。室内飼いをしていても、夏バテを起こすことがあるのをご存じですか? 夏バテは病気ではありません。夏の暑さで自律神経が乱れ、食欲不振や身体がだるいといった体調不良になることを「夏バテ」と呼んでいます。急激に体調を崩す熱中症とは異なり、数日から数週間かけて慢性的に起きるのが特徴です。 夏バテの原因は? 人と同じように、急激な室温上昇や多湿が夏バテの原因になります。猫は肉球と鼻の一部だけにしか汗腺がないため、人のように汗をかいて、気化熱によって体温を下げることが難しいそうです。さらに、日本の夏は多湿で、空気中に水分が多く含まれているため、わずかな汗でも十分に蒸発できません。その結果、身体に熱がこもり、夏バテを起こします。 また、暑さだけでなく、冷房の効き過ぎでも体調を崩すことがあります。エアコンの冷気は下にたまるため、床で涼を取る猫に冷気が当たってしまうからです。 夏バテを起こしやすい猫種 すべての猫が夏バテを起こす可能性はありますが、中でも被毛が長く熱がこもりやすい長毛種、短毛種でも被毛が二層構造になっているダブルコート、骨格上呼吸がしづらい鼻がつぶれている短頭種は、夏バテを起こしやすいと言われています。そのほかにも、身体がまだできあがっていない仔猫、身体機能が低下しているシニア猫、病気で免疫力が落ちている猫、太り気味の猫も体温調整が難しく、体調を崩しがちです。この子たちは熱中症にもかかりやすいので、注意してあげましょう。 夏バテの症状と熱中症との違い 夏バテには特徴的な症状があります。猫は本能的に体調が悪いことを隠す習性があるので、愛猫の無言のサインを見逃さないことが大切です。また、似ているようで異なる熱中症との違いも解説しますね。 【夏バテの症状】 夏バテを起こすと、次のような症状が現れます。 食欲が落ちる 暑さのせいで胃腸の働きが弱り、食欲が落ちる場合があります。普段はよく食べる子がご飯を残したり、全く食べなくなったら要注意です。 ぐったりとしている 食欲が落ちるとともに体力も低下し、だるそうにして動きが鈍くなります。 グルーミングをしない グルーミングは身体を清潔に保つ以外にも、唾液で毛を濡らし、気化熱で体温を下げる役割もあるのだそう。夏バテで身体に熱がこもると唾液が出づらくなり、グルーミングできないため、体温を下げられなくなります。毛づやがなくなることもあります。 飲む水の量と尿の量が減る 尿の量が減っている場合は、脱水症状を起こしていることがあります。この状態が長く続くと、腎臓や泌尿器系の病気にかかるリスクが高まります。 下痢や嘔吐をしている 暑さで消化器系に負担がかかるために起こる症状です。何回も続く場合は、脱水症状や他の病気にかかっているかもしれません。 【熱中症の症状】 ハアハアと苦しそうに呼吸をしている、充血をしているといった症状がある場合は、熱中症まで進行している可能性があります。さらに、泡やよだれを口から出していたら危険な状態です。気づいたときには症状が進んでいた……とならないよう、いつも以上に気をつけてあげてくださいね。 夏バテの予防策 猫は自分で環境を変えることができません。夏バテを起こしにくい部屋の状態を作れるのは飼い主さんだけです。さまざまな対策をして愛猫を守ってあげましょう。 【室温と湿度の管理】 まずは、エアコンや除湿機などを使って、猫にとって最適な室温と湿度を保つことです。日本の夏の平均湿度は50~60%と言われており、最高で75%になることもあります。猫のためには、一般的には湿度は50%前後が推奨されており、通年の推奨の室温は20~23℃前後です。夏はもう少し高くてもいいですが、空調管理はしっかり行ってください。 冷房をかけるときは、風の向きを調整したり、サーキュレーターで空気を循環させるなどして、猫に冷気が直接当たらないようにすることも大事です。...
猫の夏バテを防ぐために|快適に過ごすヒントと工夫
目次を表示する 猫の夏バテとは? いよいよ夏本番です。今年も猛暑日が続きそうですね。人の命に関わるほどのこの危険な暑さは、猫の健康も損なうことがあります。室内飼いをしていても、夏バテを起こすことがあるのをご存じですか? 夏バテは病気ではありません。夏の暑さで自律神経が乱れ、食欲不振や身体がだるいといった体調不良になることを「夏バテ」と呼んでいます。急激に体調を崩す熱中症とは異なり、数日から数週間かけて慢性的に起きるのが特徴です。 夏バテの原因は? 人と同じように、急激な室温上昇や多湿が夏バテの原因になります。猫は肉球と鼻の一部だけにしか汗腺がないため、人のように汗をかいて、気化熱によって体温を下げることが難しいそうです。さらに、日本の夏は多湿で、空気中に水分が多く含まれているため、わずかな汗でも十分に蒸発できません。その結果、身体に熱がこもり、夏バテを起こします。 また、暑さだけでなく、冷房の効き過ぎでも体調を崩すことがあります。エアコンの冷気は下にたまるため、床で涼を取る猫に冷気が当たってしまうからです。 夏バテを起こしやすい猫種 すべての猫が夏バテを起こす可能性はありますが、中でも被毛が長く熱がこもりやすい長毛種、短毛種でも被毛が二層構造になっているダブルコート、骨格上呼吸がしづらい鼻がつぶれている短頭種は、夏バテを起こしやすいと言われています。そのほかにも、身体がまだできあがっていない仔猫、身体機能が低下しているシニア猫、病気で免疫力が落ちている猫、太り気味の猫も体温調整が難しく、体調を崩しがちです。この子たちは熱中症にもかかりやすいので、注意してあげましょう。 夏バテの症状と熱中症との違い 夏バテには特徴的な症状があります。猫は本能的に体調が悪いことを隠す習性があるので、愛猫の無言のサインを見逃さないことが大切です。また、似ているようで異なる熱中症との違いも解説しますね。 【夏バテの症状】 夏バテを起こすと、次のような症状が現れます。 食欲が落ちる 暑さのせいで胃腸の働きが弱り、食欲が落ちる場合があります。普段はよく食べる子がご飯を残したり、全く食べなくなったら要注意です。 ぐったりとしている 食欲が落ちるとともに体力も低下し、だるそうにして動きが鈍くなります。 グルーミングをしない グルーミングは身体を清潔に保つ以外にも、唾液で毛を濡らし、気化熱で体温を下げる役割もあるのだそう。夏バテで身体に熱がこもると唾液が出づらくなり、グルーミングできないため、体温を下げられなくなります。毛づやがなくなることもあります。 飲む水の量と尿の量が減る 尿の量が減っている場合は、脱水症状を起こしていることがあります。この状態が長く続くと、腎臓や泌尿器系の病気にかかるリスクが高まります。 下痢や嘔吐をしている 暑さで消化器系に負担がかかるために起こる症状です。何回も続く場合は、脱水症状や他の病気にかかっているかもしれません。 【熱中症の症状】 ハアハアと苦しそうに呼吸をしている、充血をしているといった症状がある場合は、熱中症まで進行している可能性があります。さらに、泡やよだれを口から出していたら危険な状態です。気づいたときには症状が進んでいた……とならないよう、いつも以上に気をつけてあげてくださいね。 夏バテの予防策 猫は自分で環境を変えることができません。夏バテを起こしにくい部屋の状態を作れるのは飼い主さんだけです。さまざまな対策をして愛猫を守ってあげましょう。 【室温と湿度の管理】 まずは、エアコンや除湿機などを使って、猫にとって最適な室温と湿度を保つことです。日本の夏の平均湿度は50~60%と言われており、最高で75%になることもあります。猫のためには、一般的には湿度は50%前後が推奨されており、通年の推奨の室温は20~23℃前後です。夏はもう少し高くてもいいですが、空調管理はしっかり行ってください。 冷房をかけるときは、風の向きを調整したり、サーキュレーターで空気を循環させるなどして、猫に冷気が直接当たらないようにすることも大事です。...
-
COLUMN

はじめての猫との暮らしに必要なものをまとめました。
目次を表示する どんな準備をすればいいの? 昨今、リモートワークなど働き方が多様化したこともあり、猫を飼う人が増えましたが、猫と暮らすのははじめてで、不安でいっぱいです……」そんな飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか?でも、大丈夫。そんな時どんな準備をすればいいのか、具体的にご説明していきましょう。 揃えておくべき基本グッズ お迎えした日から、猫は飼い主さんと暮らし始めます。今回は家に着いたらすぐに使うものをご紹介します。準備が整ったら、楽しい猫との暮らしがスタートしますよ。 1.フードと水と食器 最初に必要となるのはフード。猫用のものは、大きく分けてドライフードとウェットフードの2種類があり、食感と水分量が違います。 猫用のフードは、年齢や健康状態で選ぶこと以外に、ドライフードだけだと水分が不足する可能性があり、ウェットフードは歯周病を起こしやすく、こまめな歯磨きケアが必要となる、ということを知っておくことが大切です。 猫の飲み水は、一般的に水道水で問題ないとされていますが、お住まいの地域によっては水道水の硬度が高く、結石のリスクを高める場合があります。水道水を与える場合は、地域の水質を調べておくと安心です。 2.トイレと猫砂 猫の祖先は砂漠で暮らしていたため、砂の上で用を足すのは本能です。 トイレが気に入らないと、粗相しちゃうなんてこともあり、下部尿路疾患のリスクも高まってしまうので、初めに気にいるトイレを見極めることが大切です。 仔猫の時は、浅くて入りやすい小さめのもので大丈夫ですが、成猫になったら大きめのトイレが良いと言われています。プラスチック製の箱に猫砂を入れるだけのノーマルタイプのほか、掃除が楽なシステムトイレや全自動トイレ、AI搭載のスマートトイレなどいろいろな種類があるので、年齢、身体の大きさ、好み、飼い主さんの手間などを総合的に考慮してトイレを選びましょう。 猫砂は、大きく分けて、鉱物系、紙系、木系、おから、シリカゲルの5種類があります。トイレの種類によって使える猫砂が決まっている場合があるので、購入前にしっかりと確認してくださいね。また、新しいトイレに戸惑っている場合は、それまで使っていたものを少し分けてもらって、入れておくと早く慣れます。自分の排泄物のにおいがするので安心するのだそう。また、固まった砂や糞を取り除くスコップも必要です。 3.キャリーケース わが家にお迎えする時、動物病院に連れて行く時、災害時に避難する時などに、キャリーケースが必要です。持ち手付きのバッグタイプ、リュックタイプやプラスチック製のハードなクレートタイプなどの形があります。 4.爪とぎと爪切り 室内で暮らす猫に欠かせないのが“爪のケア”。猫の爪の古い層を剥がすために爪とぎ、尖った爪を丸くするために爪切り、この両方が必要です。お迎えする猫が子猫の場合は、小さなうちに爪切りに慣らしてあげることも大切です。爪のケアは家具や壁紙での爪とぎを防ぐためでもあるので、ぜひご準備ください。 5.口腔ケア 猫にも歯磨きが必要です。歯周病になると、心臓病や腎臓病の原因となることがあるので、しっかり予防しておくことが大切です。成猫は嫌がる可能性が高いので、爪切り同様に、お迎えする猫が子猫の場合は、ぜひ小さいうちから慣らしてあげてください。 6.首輪と名前札 2022年6月1日よりショップで販売されるペットへのマイクロチップ装着・登録が義務化されましたが、保護団体から譲り受けることもある猫は、装着されていないことが多いといいます。被災地の保護先で身元確認にまず使われるのは、首輪と名前札です。これらは、誰かの「大切な家族である」という目印なのです。 7.おもちゃ 猫は野生で狩りをしていた名残で、年齢に関わらず、獲物を捕まえるような遊びが大好き。猫のおもちゃは、運動不足解消やストレス発散の役割もあり、健康維持のために必要不可欠なアイテムです。愛猫が喜ぶものでコミュニケーションをとることで、飼い主との絆も深まります。 関連記事:Column「猫のおもちゃの選び方ガイド」 8.ベッド 寝心地が良い寝床があれば、猫はホッとできます。保温性に優れたドームタイプ、縁がクッションになっているソファタイプ、ケージや窓などに固定するハンモックタイプなどの形があるので、愛猫の好きなものを選んであげましょう。形だけでなく素材にもこだわると、快適度が上がります。 猫にとって快適な環境を作る 必要なものを揃えたら、猫が心地よく暮らせるよう、下記のように室内の環境を整えましょう。...
はじめての猫との暮らしに必要なものをまとめました。
目次を表示する どんな準備をすればいいの? 昨今、リモートワークなど働き方が多様化したこともあり、猫を飼う人が増えましたが、猫と暮らすのははじめてで、不安でいっぱいです……」そんな飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか?でも、大丈夫。そんな時どんな準備をすればいいのか、具体的にご説明していきましょう。 揃えておくべき基本グッズ お迎えした日から、猫は飼い主さんと暮らし始めます。今回は家に着いたらすぐに使うものをご紹介します。準備が整ったら、楽しい猫との暮らしがスタートしますよ。 1.フードと水と食器 最初に必要となるのはフード。猫用のものは、大きく分けてドライフードとウェットフードの2種類があり、食感と水分量が違います。 猫用のフードは、年齢や健康状態で選ぶこと以外に、ドライフードだけだと水分が不足する可能性があり、ウェットフードは歯周病を起こしやすく、こまめな歯磨きケアが必要となる、ということを知っておくことが大切です。 猫の飲み水は、一般的に水道水で問題ないとされていますが、お住まいの地域によっては水道水の硬度が高く、結石のリスクを高める場合があります。水道水を与える場合は、地域の水質を調べておくと安心です。 2.トイレと猫砂 猫の祖先は砂漠で暮らしていたため、砂の上で用を足すのは本能です。 トイレが気に入らないと、粗相しちゃうなんてこともあり、下部尿路疾患のリスクも高まってしまうので、初めに気にいるトイレを見極めることが大切です。 仔猫の時は、浅くて入りやすい小さめのもので大丈夫ですが、成猫になったら大きめのトイレが良いと言われています。プラスチック製の箱に猫砂を入れるだけのノーマルタイプのほか、掃除が楽なシステムトイレや全自動トイレ、AI搭載のスマートトイレなどいろいろな種類があるので、年齢、身体の大きさ、好み、飼い主さんの手間などを総合的に考慮してトイレを選びましょう。 猫砂は、大きく分けて、鉱物系、紙系、木系、おから、シリカゲルの5種類があります。トイレの種類によって使える猫砂が決まっている場合があるので、購入前にしっかりと確認してくださいね。また、新しいトイレに戸惑っている場合は、それまで使っていたものを少し分けてもらって、入れておくと早く慣れます。自分の排泄物のにおいがするので安心するのだそう。また、固まった砂や糞を取り除くスコップも必要です。 3.キャリーケース わが家にお迎えする時、動物病院に連れて行く時、災害時に避難する時などに、キャリーケースが必要です。持ち手付きのバッグタイプ、リュックタイプやプラスチック製のハードなクレートタイプなどの形があります。 4.爪とぎと爪切り 室内で暮らす猫に欠かせないのが“爪のケア”。猫の爪の古い層を剥がすために爪とぎ、尖った爪を丸くするために爪切り、この両方が必要です。お迎えする猫が子猫の場合は、小さなうちに爪切りに慣らしてあげることも大切です。爪のケアは家具や壁紙での爪とぎを防ぐためでもあるので、ぜひご準備ください。 5.口腔ケア 猫にも歯磨きが必要です。歯周病になると、心臓病や腎臓病の原因となることがあるので、しっかり予防しておくことが大切です。成猫は嫌がる可能性が高いので、爪切り同様に、お迎えする猫が子猫の場合は、ぜひ小さいうちから慣らしてあげてください。 6.首輪と名前札 2022年6月1日よりショップで販売されるペットへのマイクロチップ装着・登録が義務化されましたが、保護団体から譲り受けることもある猫は、装着されていないことが多いといいます。被災地の保護先で身元確認にまず使われるのは、首輪と名前札です。これらは、誰かの「大切な家族である」という目印なのです。 7.おもちゃ 猫は野生で狩りをしていた名残で、年齢に関わらず、獲物を捕まえるような遊びが大好き。猫のおもちゃは、運動不足解消やストレス発散の役割もあり、健康維持のために必要不可欠なアイテムです。愛猫が喜ぶものでコミュニケーションをとることで、飼い主との絆も深まります。 関連記事:Column「猫のおもちゃの選び方ガイド」 8.ベッド 寝心地が良い寝床があれば、猫はホッとできます。保温性に優れたドームタイプ、縁がクッションになっているソファタイプ、ケージや窓などに固定するハンモックタイプなどの形があるので、愛猫の好きなものを選んであげましょう。形だけでなく素材にもこだわると、快適度が上がります。 猫にとって快適な環境を作る 必要なものを揃えたら、猫が心地よく暮らせるよう、下記のように室内の環境を整えましょう。...
-
COLUMN

湿度に弱い猫のための快適な空間づくり
目次を表示する 梅雨の多湿は大敵 湿度が一気に上がる梅雨。ジメジメとした日が続くと体調を崩しがちになりますよね。実は猫も、人間と同じようにこの季節には敏感です。皮膚がベタついて機嫌が悪くなったり、寝つきにくくなったり。さらに、食欲不振になることもあります。その結果、体力が落ち、さまざまなトラブルに見舞われることも。今回は、猫がなぜ湿度に弱いかという理由から、かかりやすい病気や湿度対策までを解説します。 猫が湿度に弱い理由 猫の先祖のリビアヤマネコは砂漠地帯で暮らしていたため、乾燥した暑さには強い傾向があります。でも、日本のような高温多湿の気候は苦手。肉球にしか汗腺がなく熱を逃しにくいうえ、湿度が上がると空気中の水分量が増えて、汗が蒸発しにくくなるからです。また、グルーミング時の唾液の水分が、湿度で蒸発しにくくなるのも理由の一つ。猫は、唾液が蒸発する時の気化熱で体温を下げているのです。 最適な室温と湿度は? では、どれくらいの室温と湿度が良いのでしょうか。環境省がまとめた「動物取扱業における 犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」※1によると、一般的には室温は20~23℃前後、湿度は50%前後が推奨されています。ただし、湿度に弱い子の場合は、より涼しくする必要があるとのこと。その他、猫種や習性、個体ごとの身体の特徴や健康状態によっても、最適な室温や湿度は変わりますので、愛猫にとってのベストを見つけてくださいね。 ちなみに、冬は湿度が下がるから安心と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、反対に乾燥が問題になります。湿度が20%を下回ると、静電気が起こりやすくなり、ブラッシングの際痛みを伴うことも。また、十分に水分摂取ができていないと泌尿器系の病気を発症することがあります。猫は暖かい場所で動かなくなり、水がある場所へ移動しなくなるので、気をつけてあげましょう。 多湿がもたらす健康被害 次に、梅雨から夏にかけて発症しやすい主な病気を説明します。 1.熱中症 身体の中の熱がこもり、体温が上昇することで起こるというメカニズムは、人間と同じ。口を開けてハアハア息をするようになったら要注意です。特に、長毛種や仔猫、シニア猫、太り気味の猫、骨格上呼吸がしづらい鼻がつぶれている短頭種は、かかりやすいといいます。 2.ノミやダニが原因の病気 気温が13℃になるとノミが、20℃でダニが活発になり、湿度が上がればより繁殖するので、いつも以上に配慮が必要です。たとえば、以下のようなものがあります。 ・ノミアレルギー性皮膚炎 首から背中、おしりにかけて、赤い発疹が出て、強いかゆみを伴います。かきむしってしまい、脱毛や出血が見られる場合も。 ・疥癬、耳疥癬(耳ダニ) 強いかゆみで、激しく頭を振ることがあります。黒っぽい耳あかが出るのも特徴のひとつ。 3.真菌が原因の病気 真菌はいわゆるカビで、梅雨は増殖の季節です。酵母菌、糸状菌、担糸菌に分類され、人の食べ物に効果的に使われる無害なものもありますが、有害なものもあるのです。 ・皮膚糸状菌症 糸状菌が原因で、顔、耳、手足で脱毛し、皮膚がかさかさしたりブツブツができたりして、強いかゆみを伴うこともあり。 ・マラセチア性皮膚炎やマラセチア性外耳炎 酵母菌が異常に繁殖して発生する病気です。皮膚や耳が赤くなりかゆくなります。 その他に、毛が蒸れることで急性湿性皮膚炎(ホットスポット)を発症したり、アトピー性皮膚炎が悪化したりすることもあります。かゆがっている子の姿を目にするのは、本当につらいものですよね。 適切な室内環境を保つために でも、飼い主さんのちょっとしたがんばりで、愛猫を大敵から守ることができるんです。ベストな室温と湿度を保つために、ぜひ以下のことをやってみてください。 ・こまめに換気をする こもった湿気を室外に逃がすため、窓やドアを2カ所以上開け、風の通り道を作ります。...
湿度に弱い猫のための快適な空間づくり
目次を表示する 梅雨の多湿は大敵 湿度が一気に上がる梅雨。ジメジメとした日が続くと体調を崩しがちになりますよね。実は猫も、人間と同じようにこの季節には敏感です。皮膚がベタついて機嫌が悪くなったり、寝つきにくくなったり。さらに、食欲不振になることもあります。その結果、体力が落ち、さまざまなトラブルに見舞われることも。今回は、猫がなぜ湿度に弱いかという理由から、かかりやすい病気や湿度対策までを解説します。 猫が湿度に弱い理由 猫の先祖のリビアヤマネコは砂漠地帯で暮らしていたため、乾燥した暑さには強い傾向があります。でも、日本のような高温多湿の気候は苦手。肉球にしか汗腺がなく熱を逃しにくいうえ、湿度が上がると空気中の水分量が増えて、汗が蒸発しにくくなるからです。また、グルーミング時の唾液の水分が、湿度で蒸発しにくくなるのも理由の一つ。猫は、唾液が蒸発する時の気化熱で体温を下げているのです。 最適な室温と湿度は? では、どれくらいの室温と湿度が良いのでしょうか。環境省がまとめた「動物取扱業における 犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」※1によると、一般的には室温は20~23℃前後、湿度は50%前後が推奨されています。ただし、湿度に弱い子の場合は、より涼しくする必要があるとのこと。その他、猫種や習性、個体ごとの身体の特徴や健康状態によっても、最適な室温や湿度は変わりますので、愛猫にとってのベストを見つけてくださいね。 ちなみに、冬は湿度が下がるから安心と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、反対に乾燥が問題になります。湿度が20%を下回ると、静電気が起こりやすくなり、ブラッシングの際痛みを伴うことも。また、十分に水分摂取ができていないと泌尿器系の病気を発症することがあります。猫は暖かい場所で動かなくなり、水がある場所へ移動しなくなるので、気をつけてあげましょう。 多湿がもたらす健康被害 次に、梅雨から夏にかけて発症しやすい主な病気を説明します。 1.熱中症 身体の中の熱がこもり、体温が上昇することで起こるというメカニズムは、人間と同じ。口を開けてハアハア息をするようになったら要注意です。特に、長毛種や仔猫、シニア猫、太り気味の猫、骨格上呼吸がしづらい鼻がつぶれている短頭種は、かかりやすいといいます。 2.ノミやダニが原因の病気 気温が13℃になるとノミが、20℃でダニが活発になり、湿度が上がればより繁殖するので、いつも以上に配慮が必要です。たとえば、以下のようなものがあります。 ・ノミアレルギー性皮膚炎 首から背中、おしりにかけて、赤い発疹が出て、強いかゆみを伴います。かきむしってしまい、脱毛や出血が見られる場合も。 ・疥癬、耳疥癬(耳ダニ) 強いかゆみで、激しく頭を振ることがあります。黒っぽい耳あかが出るのも特徴のひとつ。 3.真菌が原因の病気 真菌はいわゆるカビで、梅雨は増殖の季節です。酵母菌、糸状菌、担糸菌に分類され、人の食べ物に効果的に使われる無害なものもありますが、有害なものもあるのです。 ・皮膚糸状菌症 糸状菌が原因で、顔、耳、手足で脱毛し、皮膚がかさかさしたりブツブツができたりして、強いかゆみを伴うこともあり。 ・マラセチア性皮膚炎やマラセチア性外耳炎 酵母菌が異常に繁殖して発生する病気です。皮膚や耳が赤くなりかゆくなります。 その他に、毛が蒸れることで急性湿性皮膚炎(ホットスポット)を発症したり、アトピー性皮膚炎が悪化したりすることもあります。かゆがっている子の姿を目にするのは、本当につらいものですよね。 適切な室内環境を保つために でも、飼い主さんのちょっとしたがんばりで、愛猫を大敵から守ることができるんです。ベストな室温と湿度を保つために、ぜひ以下のことをやってみてください。 ・こまめに換気をする こもった湿気を室外に逃がすため、窓やドアを2カ所以上開け、風の通り道を作ります。...